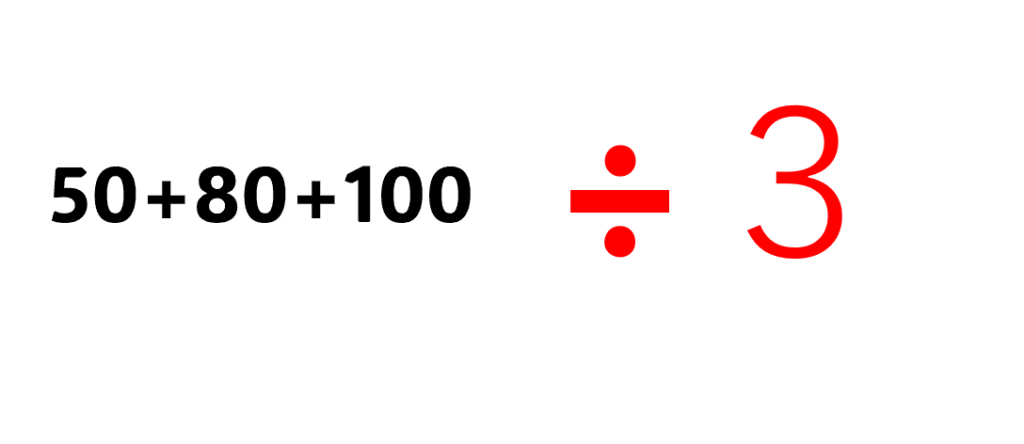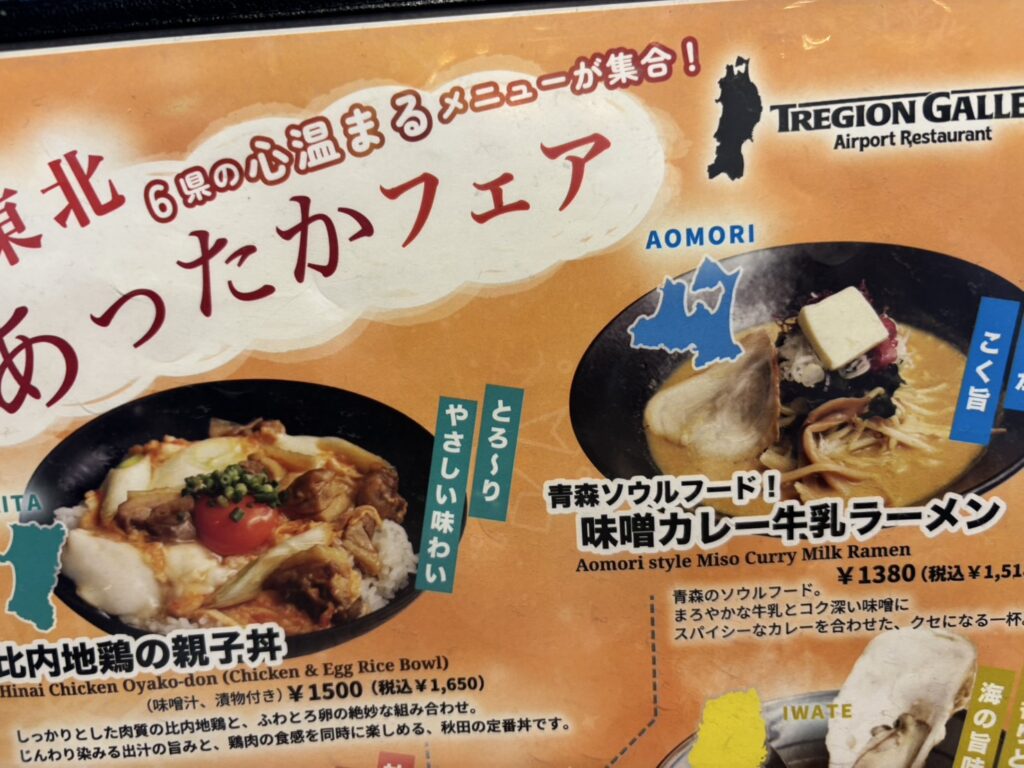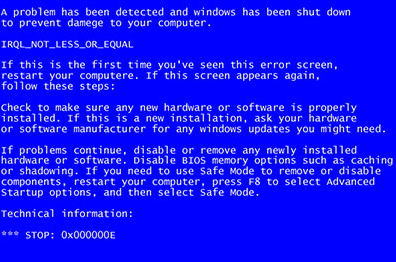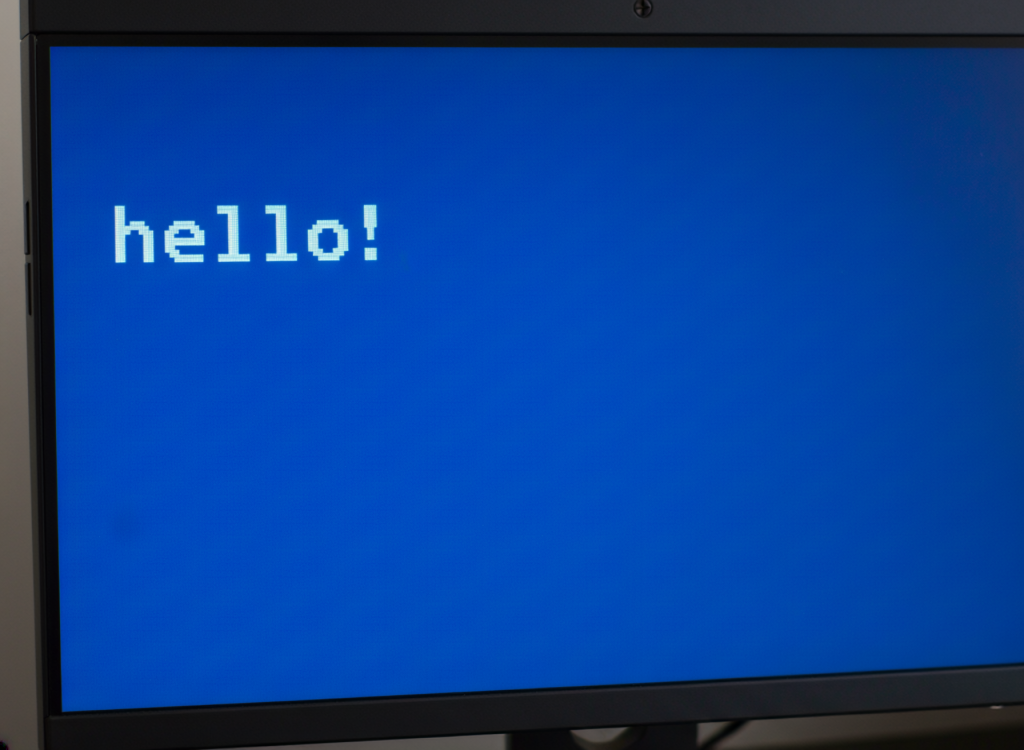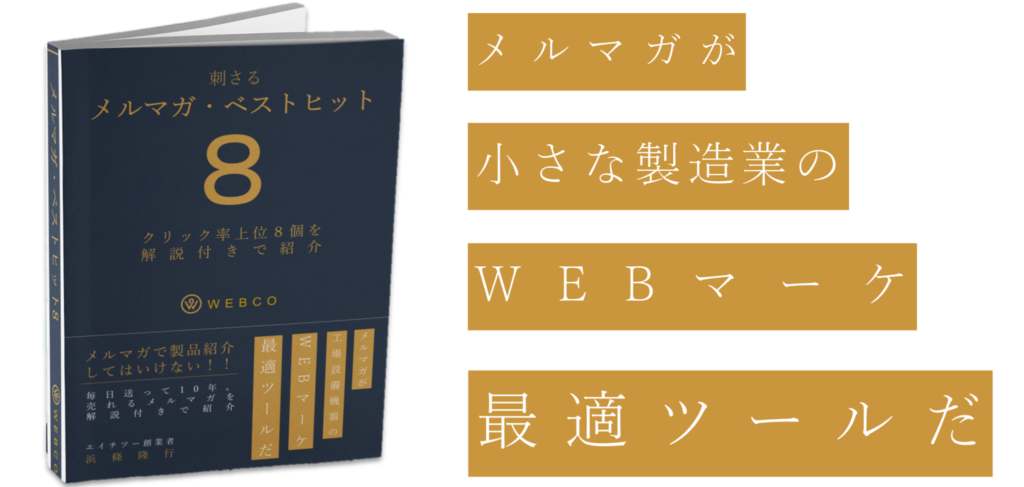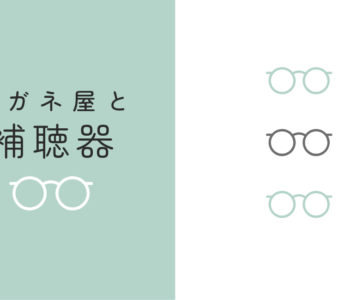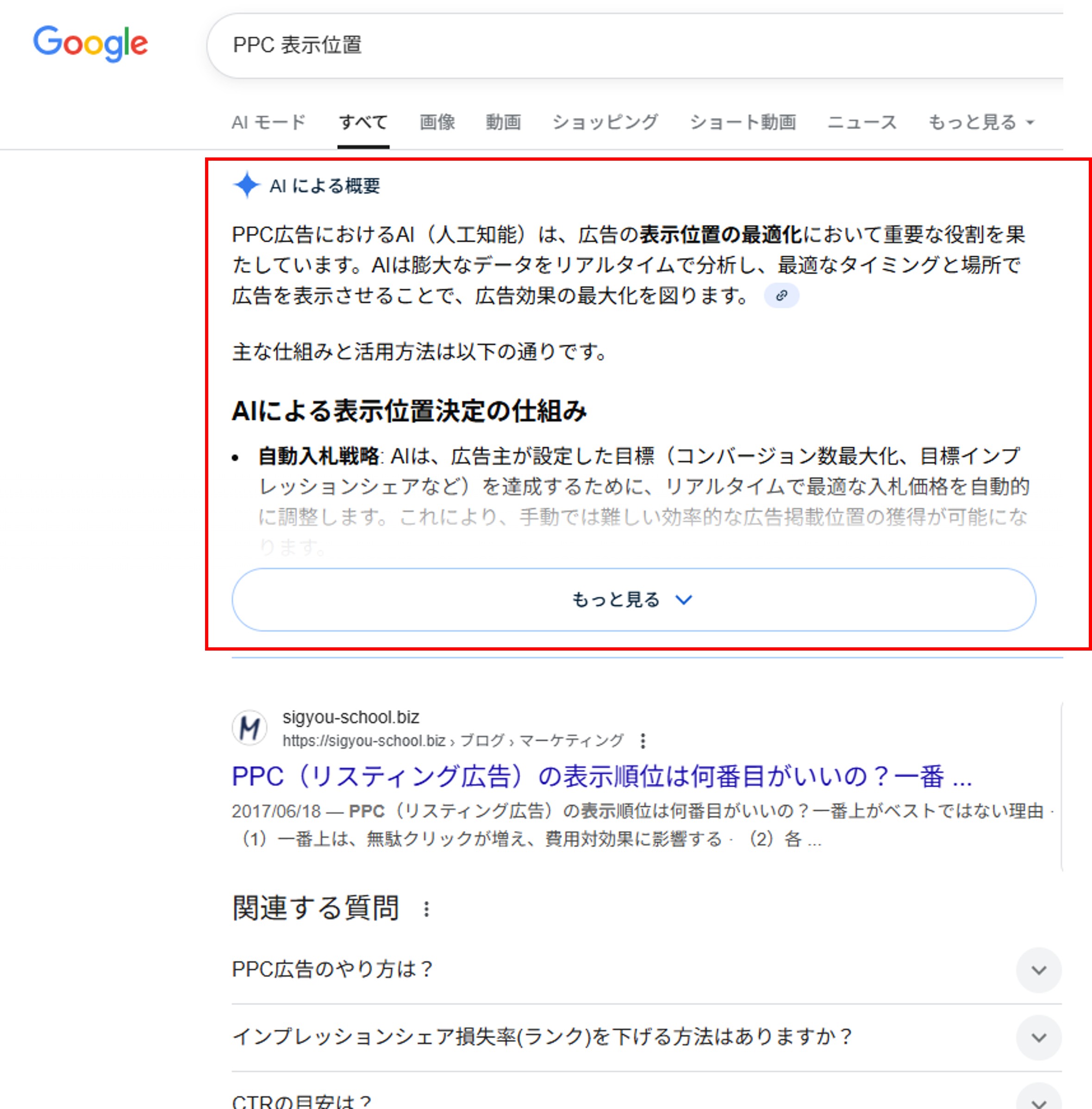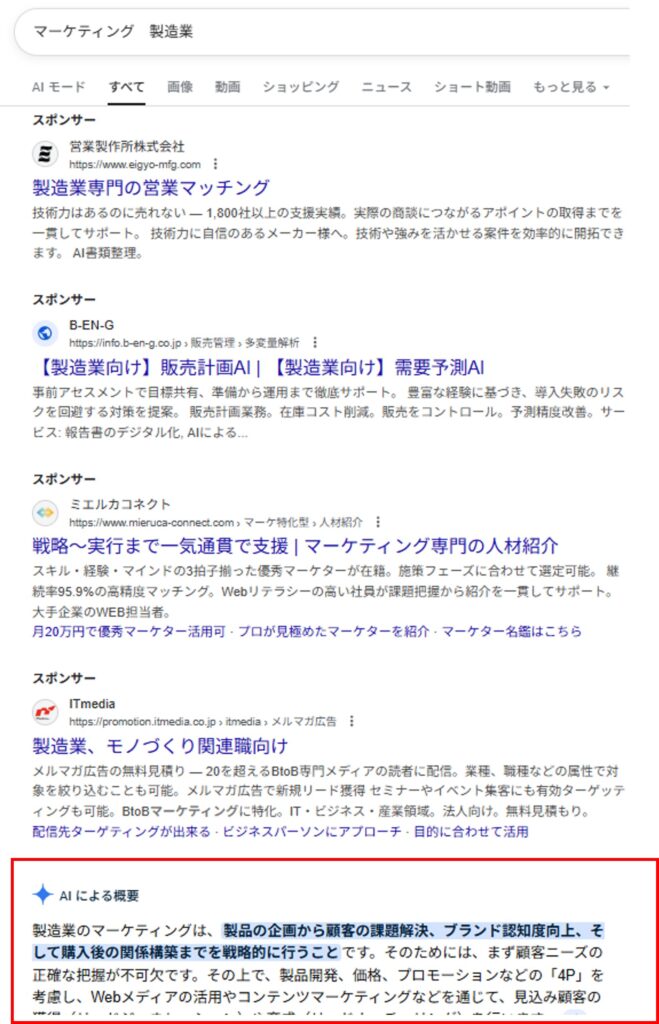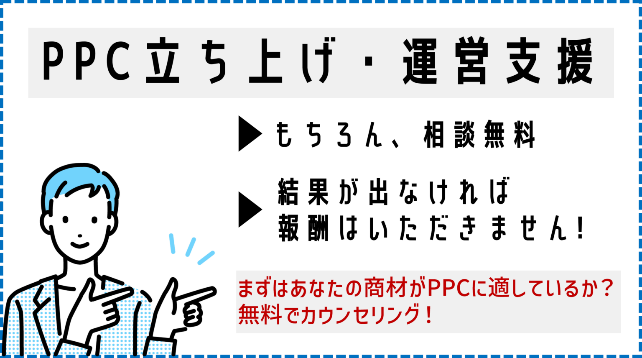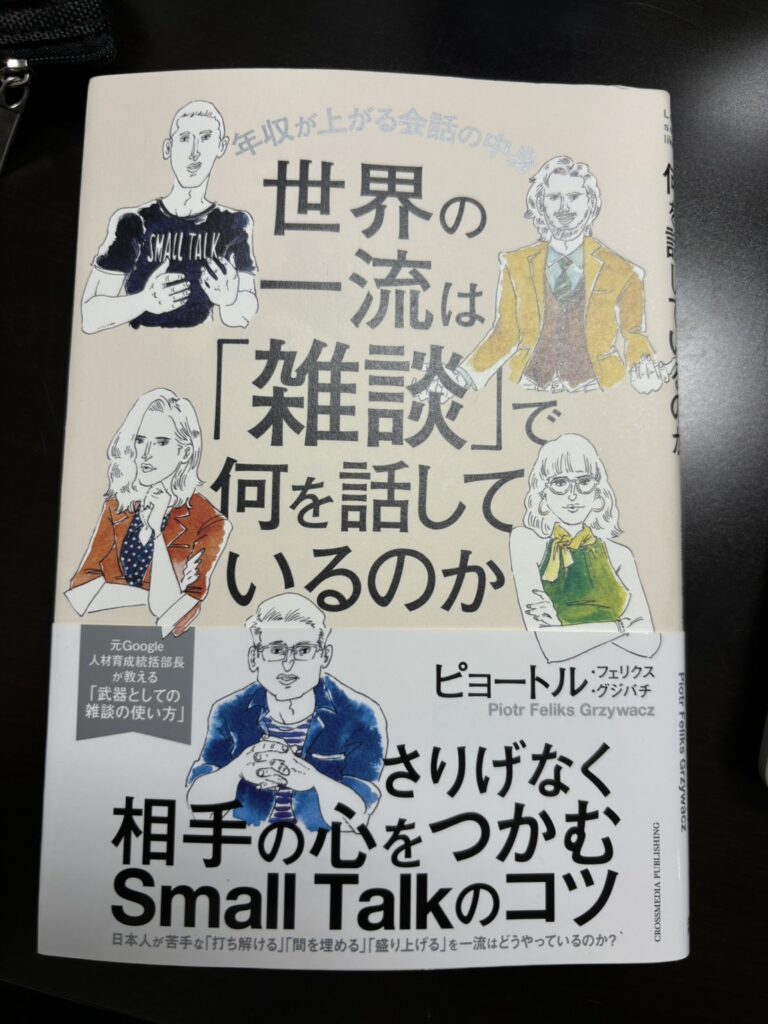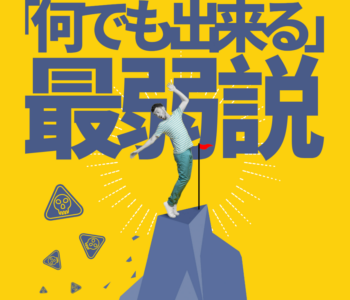 未分類
未分類
「何でもできる」は…
FROM,中島
「起用貧乏」なんて言葉がありますが、
自分は起用貧乏だよ~って思う方、ちょっと心の中でお返事を頂けますと幸いです。
正直あまりいい意味ではないので、胸を張れるものではありませんが
私も小さく返事をした一人です。
先日、お仕事の関係で新しく借りる事務所の内覧に行った時の事です。
「うわ、ほんと、こういうことだよな~。気をつけよ~。」
と、心底思うことがあったのでこの場を借りて共有しますね。
最高の物件
その物件は、まだまだ4名ほどの小さな会社ですが、
親会社に間借りしている社屋を出て、なるべく自分たちで頑張っていこう!
という思いの企業が探し当てた物件でした。
私も微力ながらその事業のフォローをさせて頂いている関係で、
内覧に立ち会うことになりました。
あまり情報が出ていない物件でしたが、
ざっくりと公表されている立地や間取り、賃料などは探している条件通りの、
まさに、最高の物件でした。
直ぐに内覧のアポを取り付け、
翌日には不動産屋の担当者さんと落ち合い、内覧が開始されました。
「本当に最高なんですよ!」
営業車から降りてきた担当者さんと、簡単な挨拶を済ませ、
まずは一階の作業スペース(ガレージ)の紹介が始まります。
ガレージとして趣味のためにも、簡単な製作や梱包など、
作業スペースとしてもお使い頂けます。
とってもお洒落で飽きが来ない壁打ちコンクリート仕様となっています。
ライトはレールが引いてあるので、お好きなところに◯×△◇・・・トイレはこちらで◯×△◇・・・勝手口が・・・
と説明が進みます。
一階の内覧を済ませ、事務所となる二階はワンルームでした。
広さは、というと今のメンバーでぴったりくらいですが、
この先事業をスケールさせていきたいという思いを考えると「少し狭いね」というのが本音でした。
実はこの事務所、2階に暮らすのに十分なサイズの脱衣所とお風呂があり、それが無ければ・・・
という非常に惜しい物件でした。
貸事務所でもOKだし、普通に賃貸としても貸し出しOKな、
マルチユース物件という物件だったようです。
「この物件、本当に最高なんですよ!住むも働くも両方できる物件なんて中々ないですよ!オススメです!」
嬉々としてプレゼンしてくれる担当者さんに挨拶し、物件を後にしました。
自社のスタイルは?
事務所として検討するには、必要ない機能が備わっていたり、
住むにはちょっと家賃高めであったり、
なんとも起用貧乏な物件でした。
帯に短しタスキに長しなんてことわざもありますが、
事務所を借りる人は住む事は考えないし、住む人は仕事の事考えないんですよね。
以上のことから、タイトルにもある「何でも出来る」は最弱か、という問いについて、
ここで改めてその回答に触れるのであれば、
最弱ではない。ただし、「何も出来ない」の次に弱い。と思っています。
せっかくなら、ついついあれもこれも!と詰め込んで訴求してしまうのもわかりますが、
それって1回(もしくは限られた回数)だけだから、だったりしないでしょうか?
我々は「毎日訴求できるツールと方法」で、
業界でも閉鎖的なポンプメーカーという業界を創業から10年以上、増収増益を続けてきました。
製造業の集客にお悩みがあれば、
製造業専門のマーケティング支援、WEBCOへご相談下さい。